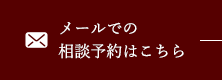2025/02/07 介護事故
介護施設における暴力行為と法的対応:高齢者・介護職員の安全を守るために知っておきたいポイント
はじめに
介護現場では、高齢者や要介護者同士の衝突や、認知症などの影響で突発的に暴力行為を起こしてしまうケースが報告されています。また、逆に介護職員が利用者に対して暴言や身体的な虐待を加える事件も、ニュースなどで耳にすることがあります。いずれの場合も、暴力行為が起きると被害者の身体的・精神的なダメージはもちろん、施設全体の信頼や職員の士気を大きく損ねる重大な問題です。
本稿では、介護施設における暴力行為をテーマに、加害者・被害者が利用者同士の場合、あるいは職員と利用者間の場合など、様々なシチュエーションについて法的な考え方と対処法を整理します。さらに、暴力行為が発生した場合の責任の所在や、施設側の安全配慮義務、弁護士に相談するメリットも解説し、問題解決の糸口をご提案します。
Q&A
Q1:利用者同士の暴力行為が起きた場合、施設は責任を負うのでしょうか?
施設側には安全配慮義務があり、利用者同士のトラブルを未然に防ぐための見守りや配置などの対策を講じる必要があります。もし事前に衝突の可能性を把握していながら十分な対応を怠っていた、あるいは人員配置が著しく不足していたなどの場合、施設の過失が認められ、損害賠償を負う可能性があります。
Q2:介護職員が利用者に対して暴力を振るった場合は?
これは明らかに職員側が加害者となりますが、民事上はまず施設(運営法人)が使用者責任を負う形が一般的です。また、職員個人に対して刑事責任(傷害罪や暴行罪)や行政処分が科されることもあります。
Q3:認知症で判断力が低下した利用者が職員を殴ったりした場合はどうなりますか?
認知症による意思能力の低下が認められると、利用者本人に民事上の責任を問うのは難しい場合があります。その場合、施設の管理・監督義務や家族の監督義務(在宅の場合)が検討されます。職員が怪我を負った場合、労災として補償されるケースもあります。
Q4:暴力が常習化している利用者がいて、被害が繰り返される場合は?
施設はケアプランや対応マニュアルを見直し、転倒などの事故と同様にリスクアセスメントを強化しなければなりません。必要に応じて専門医や精神科の受診を検討し、安全を確保する義務があります。対応が不十分で被害が続くと、被害者から施設側に過失責任を追及されるリスクが高まります。
Q5:暴力による精神的なダメージ(PTSDなど)も損害賠償の対象になりますか?
可能性はあります。身体的な傷害だけでなく、精神的苦痛も損害賠償の対象となり得ます。診断書やカウンセリングの記録などをもとに慰謝料を請求できる場合があります。
解説
暴力行為における法的責任の考え方
- 利用者同士の暴力
- 施設の安全配慮義務:十分な人員配置や監督体制を整えていたか
- 利用者の要介護度や認知症の有無:衝突リスクが高い状況を把握していたか
- 施設の管理責任:事故が起きる前に事前兆候がありながら放置していなかったか
- 職員から利用者への暴力
- 使用者責任(民法715条):職員が業務の執行中に違法行為を行った場合、まず施設(法人)が賠償責任を負う。
- 職員個人の刑事責任:暴行罪や傷害罪が成立する可能性。行政処分や失職のリスク。
- 利用者から職員への暴力
- 認知症や意思能力の問題:責任能力を欠く場合、民事上の賠償は家族や施設が検討対象となる。
- 労災保険:職員が業務中に負傷した場合、労働者災害補償保険の適用が考えられる。
暴力行為の防止策
- リスクアセスメント:利用者の性格や認知状態、トラブル履歴を分析し、衝突リスクを把握する
- 人員配置の適正化:夜間や休日など、スタッフが少なくなる時間帯も含めて十分な見守りを確保する
- 職員研修:暴力行為を引き起こしやすい利用者への対応方法、言葉がけや介助技術の向上
- 物理的環境の整備:衝突が起きやすい場所のレイアウト変更、個室対応や間仕切りの活用など
事故後の手続き
- 医療機関での受診(被害者)
怪我や精神的ダメージが疑われる場合は早急に受診し、診断書を取得する。 - 施設への報告・事故報告書の確認
施設が作成する事故報告書で、暴力行為の経緯や当事者、目撃者の証言を確認。 - 示談交渉または法的手段
施設が過失を認める場合は示談で解決することが多いが、否定する場合は裁判で争われる可能性あり。
弁護士に相談するメリット
- 過失の立証と責任主体の明確化
暴力行為が発生した背景には、施設の監督不行き届きや人員不足など、多角的な要因が存在します。弁護士が事故報告書や証言を精査し、誰にどの程度の過失があるのかを法的に整理します。 - 交渉・裁判手続きの代理
感情的になりやすい暴力事件では、当事者同士の話し合いがこじれることも多いです。弁護士が代理人として主張を組み立て、法律に基づいた解決へ導きやすくなります。 - 損害項目の網羅的評価
治療費や慰謝料だけでなく、仕事を休んだ場合の休業損害、後遺症が残ったときの逸失利益など、多面的に算定して請求額を確定します。 - 再発防止策の提案
暴力トラブルの多くは、施設のケアプランや人員配置の改善で発生リスクを下げることが可能です。和解案や示談書に具体的な防止策を含めるよう提言することも期待されます。
まとめ
介護施設での暴力行為は、利用者同士、あるいは利用者と職員の間で起こりうる深刻なトラブルです。身体的被害だけでなく、精神的な傷や施設への信頼低下など、多大な影響を及ぼします。施設側には、こうした事態を防ぐためにリスクアセスメントやスタッフ教育、十分な人員配置を行う義務があります。万一、暴力行為が発生してしまったら、まずは被害者のケアと事故状況の正確な把握が重要です。
トラブルが長期化し、責任の所在や賠償額で折り合いがつかない場合は、早めに弁護士へ相談し、法的根拠をもとに示談交渉や裁判手続きへ進むことを検討してください。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、介護施設内での暴力行為に関するご相談から問題解決まで、多角的なサポートを提供しております。
【弁護士法人長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル 】
企業法務に関する問題を解説したYoutubeチャンネルを運営しています。
ぜひご視聴・ご登録ください。
【メールマガジンのご案内】
無料WEBセミナー開催のお知らせや、事務所からのお知らせをメールで配信しています。
ぜひこちらのご登録もご検討ください。