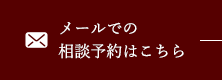2025/10/12 コラム
労災事故で会社に損害賠償請求は可能か?労災保険との関係と請求の手順
はじめに
労災保険の給付は、完全な救済ではないという事実
業務中や通勤中に発生した事故により、お怪我を負われた皆様、そして大切なご家族を亡くされたご遺族の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。突然の出来事に心身ともに大きな負担を強いられ、今後の生活や仕事について計り知れないご不安を抱えていらっしゃることと存じます。
仕事が原因で発生した傷病(労働災害、略して「労災」)については、まず国が管掌する「労働者災害補償保険(労災保険)」から、治療費や休業中の生活費などの給付を受けることが基本的な流れとなります。多くの方が、「労災保険の手続きをすれば、必要な補償はすべて受けられる」とお考えかもしれません。しかし、その認識は、時としてご自身の正当な権利を大きく見過ごす原因となり得ます。
労災保険は、被災された労働者の生活を迅速に保障するための、非常に重要なセーフティネットです。しかし、この制度はあくまで「最低限の生活保障」を目的としており、事故によって被ったすべての損害を完全に填補(てんぽ)するものではありません。特に、事故によって受けた精神的な苦痛、すなわち「慰謝料」は、労災保険の給付対象には一切含まれていないのです。
もし、あなたの遭われた事故の原因が、会社の安全管理体制の不備や、他の従業員の過失にある場合、労災保険からの給付とは全く別に、会社に対して民事上の損害賠償を請求できる可能性があります。本稿では、この「労災保険」と「会社への損害賠償請求」という二つの制度の根本的な違いを明らかにし、会社に対してどのような損害を、どのような法的根拠に基づいて請求できるのかを、専門家の視点から解説します。労災保険を受け取ったからといって諦める必要はありません。あなたが受けたすべての損害に対する正当な賠償を得るための道筋を整理しました。
補償の二本柱:労災保険と損害賠償請求の比較
労災事故に遭われた方が受けられる補償には、大きく分けて二つの制度が存在します。一つは「労災保険制度」、もう一つは「会社に対する民事上の損害賠償請求」です。この二つは目的も、根拠となる法律も、そして補償の内容も異なる、独立した制度です。両者の違いを正確に理解することが、ご自身の権利を最大限に活用するための第一歩となります。
労災保険制度:迅速な生活保障のための「無過失責任」制度
労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して、迅速かつ公正な保護をすることを目的としています。この制度の最大の特徴は、「無過失責任主義」を採用している点にあります。つまり、労災事故の発生について会社に過失(責任)があったかどうかを問わず、仕事が原因であると認定されれば、保険給付がなされます。これは、被災した労働者やその家族の生活が困窮することのないよう、速やかに最低限の生活保障を行うことを最優先しているためです。
主な給付内容には、治療費にあたる「療養(補償)給付」、休業中の所得を補填する「休業(補償)給付」、後遺障害が残った場合の「障害(補償)給付」、そして不幸にも亡くなられた場合の「遺族(補償)給付」などがあります。しかし、前述の通り、この制度はあくまで生活保障を主眼としており、事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料は一切支払われません。
会社への損害賠償請求:全損害の回復を目指す「過失責任」制度
一方、会社への損害賠償請求は、民法や労働契約法といった法律を根拠とします。こちらの目的は、被害者が事故によって被った「すべての損害」を金銭的に評価し、その全額を回復することにあります。労災保険制度とは対照的に、こちらは「過失責任主義」に基づきます。つまり、損害賠償を請求するためには、事故の発生について会社側に何らかの法的な責任(過失)があったことを証明する必要があります。
この請求における最大のポイントは、労災保険ではカバーされない損害、特に「慰謝料」を請求できる点です。事故による痛みや恐怖、将来への不安、後遺障害を背負って生きていくことの絶望感、ご家族を失った悲しみといった精神的苦痛は、会社に直接その責任を問うことによってのみ、金銭的な賠償を受けることができるのです。
|
比較項目 |
労働者災害補償保険(労災保険) |
会社への損害賠償請求 |
|---|---|---|
|
法的根拠 |
労働者災害補償保険法 |
民法、労働契約法 |
|
制度の目的 |
迅速な生活保障(最低限の補償) |
被害者が被った全損害の回復 |
|
会社の責任 |
不要(無過失責任) |
必要(過失責任) |
|
慰謝料(精神的損害) |
支払われない |
請求の中心となる |
|
休業損害の補償 |
給付基礎日額の約8割(6割+特別支給金2割) |
実際の損害額の100% |
|
手続き |
労働基準監督署への行政手続き |
会社・保険会社との交渉、労働審判、訴訟 |
この表が示すように、二つの制度は相互に補完し合う関係にあります。労災保険で当座の生活費や治療費を確保しつつ、それで補いきれない損害(特に慰謝料や休業損害の差額など)について、会社の責任を追及し、損害賠償請求を行っていくというのが、法的に認められた正しい手順なのです。
会社の責任を問う:損害賠償請求を支える2つの法的根拠
会社に対して損害賠償を請求するためには、事故の発生が「会社のせいである」と法的に認めさせる必要があります。そのための強力な法的根拠となるのが、「安全配慮義務違反」と「使用者責任」という二つの考え方です。
安全配慮義務違反(労働契約法第5条)
「安全配慮義務」とは、会社(使用者)が、労働者の生命や身体、健康を危険から守り、安全な環境で働けるように配慮する義務のことです。この義務は、かつては判例によって認められてきましたが、労働契約法第5条によって明確に法律上の義務として規定されました。
労働契約法 第五条
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
この「必要な配慮」は非常に広範な内容を含んでおり、会社がこれを怠った結果として事故が発生した場合、「安全配慮義務違反」として損害賠償責任を負うことになります。具体的には、以下のようなケースが典型例です。
- 物理的な作業環境の不備
- プレス機や裁断機などの危険な機械に、法律で定められた安全カバーやセンサーが設置されていなかった、または故障したまま放置されていた。
- 高所作業にもかかわらず、手すりや安全帯を設置・使用させる指示を怠った。
- 床が油や水で濡れて滑りやすい状態であったにもかかわらず、清掃や注意喚起をしていなかった。
- 有毒な化学物質を扱う作業場で、適切な換気設備や保護具を提供していなかった。
- 業務プロセスや人的管理の欠陥
- フォークリフトの運転など、資格が必要な業務を無資格の従業員に行わせていた。
- 十分な安全教育や訓練を実施しないまま、危険な作業に従事させた。
- 過労死ライン(月80時間超)を大幅に超えるような長時間労働を恒常的に強い、従業員の心身の健康を害した。
- 台風や大雪などの悪天候が予測される中で、屋外での危険な作業を強行させた。
これらの例のように、会社が「事故が起こるかもしれない」という危険を予見できたにもかかわらず、それを回避するための対策を怠った場合に、この義務違反が認められます。
使用者責任(民法第715条)
「使用者責任」とは、従業員(被用者)が業務の執行中に、その過失(不注意)によって第三者(この場合は同僚であるあなた)に損害を与えた場合、その従業員本人だけでなく、彼を雇用している会社(使用者)もまた、損害賠償の責任を負わなければならない、という原則です。これは民法第715条に定められています。
この責任の根拠は、会社は従業員を使って利益を上げている以上、その活動に伴って生じるリスク(損害)についても責任を負うべきであるという「報償責任」の考え方に基づいています。
使用者責任が問われる典型的なケースは以下の通りです。
- 同僚が運転するフォークリフトや社用車にひかれて怪我をした。
- 上司の間違った、あるいは危険な作業指示に従った結果、事故に遭った。
- 建設現場で、上層階で作業していた別の会社の作業員が落とした工具が当たって負傷した(この場合、その作業員を雇用する会社に対して使用者責任を追及します)。
安全配慮義務違反が「会社の仕組みや管理体制そのもの」の不備を問うものであるのに対し、使用者責任は「他の従業員の具体的な行為」を原因とする場合に適用されるのが一般的です。実際の労災事故では、これら両方の責任が同時に認められることも少なくありません。
賠償額の算定:労災保険では補えない「全損害」の内訳
会社への損害賠償請求では、労災保険の給付対象とならない損害、および給付額が不十分な損害の差額分を請求していくことになります。その内訳は多岐にわたりますが、ここでは主要な項目について、その算定方法とともに解説します。
慰謝料(精神的損害)
会社への損害賠償請求において、最も中心的な項目であり、金額的にも大きなウェイトを占めるのが慰謝料です。これは、事故によって被った精神的な苦痛に対する賠償であり、労災保険からは一切支払われません。慰謝料は、損害の態様に応じて主に3種類に分類されます。
入通院慰謝料
事故による怪我で、入院や通院を余儀なくされたこと自体の精神的苦痛に対する賠償です。原則として、治療期間(入院期間と実通院日数を考慮)に応じて算定されます。重傷であればあるほど、また治療が長期にわたるほど、金額は高額になります。
後遺障害慰謝料
治療を尽くしても残念ながら症状が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合の、将来にわたる精神的苦痛に対する賠償です。労災保険の障害等級認定(第1級から第14級)に準じて、裁判上の基準(相場)が形成されています。等級が重くなるほど、その金額は飛躍的に増大します。
|
後遺障害等級 |
慰謝料の裁判基準(目安) |
|
第1級 |
2,800万円 |
|
第2級 |
2,370万円 |
|
第3級 |
1,990万円 |
|
第7級 |
1,000万円 |
|
第12級 |
290万円 |
|
第14級 |
110万円 |
死亡慰謝料
被害者の方が亡くなられた場合の、ご本人が死に至るまでの苦痛と、ご遺族が近親者を失ったことによる悲嘆に対する賠償です。これも裁判上の基準があり、亡くなられた方の家庭内での立場(一家の支柱であったか、母親・配偶者であったかなど)によって金額が変動します。
-
- 一家の支柱の場合:2,800万円程度
- 母親、配偶者の場合:2,500万円程度
- その他の場合(独身者、子供など):2,000万円~2,500万円程度
労災保険の給付を上回る経済的損害
休業損害の差額
労災保険から支給される休業(補償)給付は、事故前3ヶ月間の平均賃金(給付基礎日額)の約6割です。これに加えて、社会復帰促進等を目的とする休業特別支給金として約2割が支給されるため、合計で収入の約8割が補填されます。しかし、本来得られるはずだった残りの約2割(厳密には4割)は失われたままです。会社への損害賠償請求では、この差額部分を含めた100%の補償を求めることができます。
逸失利益の差額
後遺障害が残ったり、死亡したりしたことで、将来にわたって得られなくなった収入(逸失利益)についても同様です。労災保険から障害(補償)年金や遺族(補償)年金が給付されますが、これはあくまで生活保障が目的であり、民事裁判で算定される逸失利益の全額に満たないケースがほとんどです。その差額分を会社に請求することができます。
その他
将来にわたって必要となる介護費用、車椅子や義足などの購入費用、自宅のバリアフリー化改修費用なども、医師の指示などに基づき必要性が認められれば、損害として請求することが可能です。
賠償金調整の仕組み:損益相殺と過失相殺の重要知識
会社に請求する損害賠償額を最終的に確定させる上で、重要な「損益相殺」と「過失相殺」という二つのルールについて理解しておく必要があります。
損益相殺:二重取りを防ぐための調整
「損益相殺」とは、被害者が一つの事故を原因として、損害を被ると同時に利益も得た場合に、その利益分を損害賠償額から差し引くという考え方です。これは、被害者が実際の損害額を超えて利得する「二重取り」を防ぎ、公平な損害の填補を実現するためのルールです。
労災事故においては、労災保険から給付された保険金(例:休業補償給付、障害補償給付)は、会社に請求する損害賠償金のうち、同じ性質を持つ損害項目(例:休業損害、逸失利益)から差し引かれます。
しかし、ここで専門家として強調したい重要な例外があります。それは、労災保険から給付される「特別支給金」(休業特別支給金、障害特別支給金など)の扱いです。判例上、これらの特別支給金は、損害の填補を目的とするものではなく、被災労働者の社会復帰の促進などを目的とした福祉的な性質の給付であるとされています。そのため、特別支給金は損益相殺の対象とならず、損害賠償額から差し引かれません。
これは、被害者にとっては非常に有利な扱いです。例えば休業損害の場合、労災保険から給付基礎日額の2割相当額が「休業特別支給金」として支給されますが、この金額は受け取った上で、さらに会社に対しては休業損害の100%を請求できる(そこから休業補償給付の6割分は引かれます)ということになります。この知識の有無が、最終的に手にする賠償額に大きな差を生むことがあるのです。
過失相殺:労働者側の過失が問われるケース
「過失相殺」とは、発生した損害について、被害者(労働者)側にも不注意(過失)があった場合に、その過失の程度に応じて損害賠償額を減額するというルールです。
例えば、「会社が安全帯の使用を指示し、現場にも用意していたにもかかわらず、労働者が面倒くさがって使用せずに高所作業を行い墜落した」といったケースでは、労働者側にも一定の過失があったと判断され、賠償額が減額される可能性があります。
ただし、会社は労働者に対して安全な労働環境を提供する包括的な義務を負っているため、労働者側の過失が認められるケースは限定的です。単なる作業ミスやヒューマンエラーの多くは、むしろそれを防ぐための管理体制を構築していなかった会社の安全配慮義務違反が問われるべき問題です。裁判例を見ても、労働者側の過失割合は2割~3割程度に留まることが多いですが、危険な作業を自覚しながら安全指示を無視したような悪質なケースでは5割以上の過失が認定されることもあります。一方で、労働者には危険を回避する術がなかったと判断され、過失相殺が一切認められないケースも存在します。
まとめ
正当な権利の実現に向けたロードマップ
業務中・通勤中の事故に遭われたら、まず何よりもご自身の治療に専念し、同時に速やかに労災保険の申請手続きを進めてください。これは、当面の生活と治療を安定させるための最優先事項です。
そして、少し落ち着かれた段階で、事故の状況を冷静に振り返ってみてください。もし、その事故の背景に「会社の安全対策が不十分だったのではないか」「上司の指示に無理があったのではないか」といった疑念が少しでも浮かぶのであれば、「労災保険だけでは、受けた損害のすべては回復できない」ということを思い出してください。
特に、事故によって心と身体に刻まれた深い傷、その精神的苦痛に対する「慰謝料」は、会社の責任を法的に追及しなければ、一円たりとも受け取ることはできません。
会社の責任の有無を法的に判断し、裁判基準に基づいた適正な賠償額を算定し、そして会社やその代理人である保険会社と対等に交渉することは、法律の専門家でなければ困難です。労災事故に遭われたら、ご自身やご家族だけで抱え込むことなく、できるだけ早い段階で、労働災害の問題に精通した弁護士にご相談ください。それが、あなたの失われた未来を取り戻すための一歩となります。
【弁護士法人長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル 】
企業法務に関する問題を解説したYoutubeチャンネルを運営しています。
ぜひご視聴・ご登録ください。
【メールマガジンのご案内】
無料WEBセミナー開催のお知らせや、事務所からのお知らせをメールで配信しています。
ぜひこちらのご登録もご検討ください。