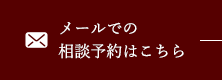2025/04/01 学校事故
通学中の事故と学校の責任:交通事故・不審者対策から考える安全配慮義務
はじめに
子どもが毎日利用する通学路には、交通事故や不審者被害などさまざまな危険が潜んでいます。通学中に起こる事故は学校外で発生するケースが多いため、学校の責任が直接問われにくい面もありますが、「学校側が危険箇所を把握していながら対策を怠っていた」「不審者の出没情報を共有せず指導もしなかった」などの事情があれば、学校の安全配慮義務違反が議論される可能性があります。
本稿では、通学中の事故について、法的観点や学校の責任の範囲、事故後の対応方法などを整理します。保護者が事故を防ぐためにできること、万一事故が起きたときにどのように動けば良いかを解説し、さらに弁護士に相談する重要性を示します。
Q&A
Q1:通学中の交通事故では、まず加害運転者が責任を負うのですか?
一般的には、交通事故の加害車両を運転していたドライバーが第一義的な責任を負います。ですが、事故箇所が学校の指定する通学路だったり、事前に危険性が指摘されていたのに学校が何ら通学指導をしなかったなどの事情があれば、補助的に学校(公立なら自治体)の過失が問われる可能性もあります。
Q2:不審者被害が通学途中で起きた場合、学校には責任があるのでしょうか?
通学路は学校の敷地外ですが、学校は安全配慮義務の一環として、不審者情報を把握したら迅速に保護者や生徒に周知し、安全指導を行う役割があります。これを怠っていた結果、被害を防げたかもしれない状況で事故が起きれば、学校の過失が議論される可能性はあります。ただし敷地外の不慮の事件として責任が否定されることも少なくなく、ケースバイケースです。
Q3:通学中の事故でどんな損害が認められますか?
交通事故なら、治療費や入院費、慰謝料、休業損害(保護者が看護で仕事を休む場合)などが典型的です。不審者被害では身体的傷害はもちろん、精神的苦痛(PTSDなど)も賠償の対象となり得ます。
Q4:事故を防ぐために保護者や地域ができることは何でしょう?
主に、
- 危険箇所の見回りやスクールゾーン整備要望
- 見守り活動(PTA・地域住民が通学路に立つなど)
- 警察や自治体に定期的に意見を出す
- 不審者情報のSNSやアプリでの共有
などが挙げられます。
Q5:学校が「通学は自己責任」と主張する場合、保護者はどう対応すれば良いですか?
学校敷地外であっても、危険箇所の把握や不審者情報の共有など、一切の責任を放棄することはできません。感情的に対立するより、弁護士を通じて法的に学校の過失がどこにあるのか示していくことで、対話を改善しやすいケースが多いです。
解説
敷地外での学校責任の範囲
通学路は道路管理者が自治体や国(警察を通じた交通規制)となるため、学校の直接的管理権限は限られます。しかし、通学指導や危険情報の周知など、学校が把握し得るリスクに対して指導を行わなかった過失が認定されれば、補助的に不法行為責任を追及される可能性があります。
事故後のステップ
- 警察・医療機関
交通事故や不審者被害なら警察に通報し、怪我があれば病院へ行き診断書を入手。 - 学校・教育委員会への連絡
公立校は自治体、私立校は学校法人と協議し、事故の原因や学校の安全指導状況を確認。 - 示談・裁判
加害者(運転者、不審者)との交渉が優先されるが、学校の過失も問う場合、示談もしくは裁判での立証が必要になる。
弁護士に相談するメリット
- 責任の整理
加害者の一次責任に加え、学校や自治体の過失を併せて主張する場合、法律の専門知識が役立つ。 - 損害項目の請求
治療費や慰謝料だけでなく、後遺障害や通学不能による逸失利益などを含めた総合的な賠償請求が可能。 - 加害者・学校・保険会社との交渉
事故が複数の責任主体を含む場合、弁護士が全体の交渉を整理して効率的に進められる。 - 再発防止策
和解や示談書に、通学路の改善や学校の指導強化を盛り込むことで、将来の事故防止が期待できる。
まとめ
通学中の事故は、児童・生徒の身体的・精神的被害だけでなく、家族にも大きな負担や不安をもたらします。交通事故の場合、主たる責任は加害運転者にあり、不審者被害なら犯人が特定されればそちらが被告となりますが、学校が危険情報を把握していながら指導や注意喚起を怠ったような場合には、安全配慮義務の不備として学校や自治体の責任が問われることもあり得ます。
事故後はまず警察や医療機関の対応を優先し、次に学校側の態度や報告書、指導体制を確認しましょう。話し合いで解決が難しければ、弁護士に相談し、過失割合や損害項目を整理して示談・裁判を検討することが大切です。弁護士法人長瀬総合法律事務所では、学校事故の解決に向け、法的ノウハウを持ってサポートしております。
【弁護士法人長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル 】
企業法務に関する問題を解説したYoutubeチャンネルを運営しています。
ぜひご視聴・ご登録ください。
【メールマガジンのご案内】
無料WEBセミナー開催のお知らせや、事務所からのお知らせをメールで配信しています。
ぜひこちらのご登録もご検討ください。