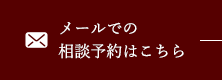2025/03/21 介護事故
介護施設での窒息事故と損害賠償:誤嚥リスクと安全管理の徹底ポイント
はじめに
高齢者や要介護者は、嚥下機能の低下や認知機能の影響で、日常の食事が大きなリスクとなり得ます。特に窒息事故は介護施設で発生した場合、わずかな時間で重篤な状態に陥る可能性があり、最悪の場合は死亡に至ることも珍しくありません。食事形態の誤りや見守りの不足、誤嚥の初期サインを見逃すなどのヒューマンエラーが原因となることが少なくありません。
本稿では、介護施設における窒息事故を解説し、その原因や法的責任、事故を防ぐための対策、そして事故発生後の家族・利用者側の対応や弁護士への相談メリットなどをお伝えします。
Q&A
Q1:なぜ高齢者は窒息事故を起こしやすいのですか?
加齢による嚥下機能の低下や、認知症などにより食べ物をうまく噛めない・飲み込みづらいといった問題があるからです。さらに口腔ケアが不十分だと唾液の分泌が少なく、誤嚥リスクが高まります。
Q2:介護施設はどのような対策をとるべきでしょうか?
一般的には、
- 専門家(ST=言語聴覚士など)による嚥下評価
- 食事形態の調整(刻み食、ミキサー食、ゼリー食など)
- 見守りや介助の徹底(個別指導計画に基づく)
- 緊急時対応マニュアル(窒息時の異物除去や蘇生措置)
などが必要とされます。
Q3:施設が窒息事故について責任を問われるのはどんなケースですか?
施設として把握可能だった嚥下リスクを無視し、通常食を提供するなど、事前対策を怠った場合が典型です。また、食事介助を担当している職員が利用者の様子を確認せず離れてしまったり、助けを呼ばれない環境で食事させたりした結果、防げたはずの窒息が起きた場合、施設の過失が認められる可能性があります。
Q4:事故後、どのように賠償が決まるのでしょうか?
まずは事故報告書などで施設の対応や不備が確認され、窒息事故の原因と過失が特定されます。施設や保険会社との示談交渉で合意できないときは最終的に裁判で過失割合や損害金額を争うことになります。損害項目としては、治療費や入院費、後遺症があれば後遺障害に基づく逸失利益、精神的苦痛の慰謝料などが含まれます。
Q5:家族が在宅介護をしている場合に窒息事故が起きても、介護保険では補償してくれませんか?
介護保険はあくまでもサービス費用の一部補助であり、窒息事故の賠償を直接担う制度ではありません。自宅で事故が起きた場合、家族の監督義務や不可抗力の有無が問われる場合もありますが、賠償保険などを活用できない限り、制度面での補償は期待しづらいです。
解説
窒息事故と施設の安全配慮義務
介護施設は、利用者の体力・嚥下機能を把握し、食事内容や介助方法を選択する義務があります。特に、嚥下リスクが高い利用者にはミキサー食やとろみ食などを提供し、複数の職員による見守りや経口摂取が困難な場合の経管栄養などを検討しなければなりません。これらの措置を怠っていた場合は、施設の管理責任や不法行為責任が問われる可能性があります。
事故後の手続きと対応
- 緊急対応
窒息事故が起きたら、速やかに応急処置(背部叩打法やハイムリック法など)を試み、必要なら救急車を呼ぶ。 - 医療機関での検査・治療
一時的に窒息が解消されたように見えても、誤嚥性肺炎などのリスクが残る場合があるため、医師の診察を受ける。 - 事故報告書の確認
施設が作成する報告書やケア記録、個別計画を精査し、不備や虚偽がないかチェック。 - 示談・法的措置
施設が過失を認めるなら示談が可能だが、否定されれば裁判へ。
事例の一例
- 誤嚥リスクのある利用者に通常食を提供
本人が普段から嚥下困難を訴えていたが、ケア計画に反映されておらず、やわらか食やとろみ食を用意しなかったため窒息死亡。 - 人手不足による見守り不足
夜間帯に1人の職員が多くの利用者を担当し、食事介助が行き届かないまま利用者が喉を詰まらせ重体に。
弁護士に相談するメリット
- 専門知識と証拠収集
窒息事故の背景には、嚥下機能評価やケアマニュアルなど専門的な要素が含まれます。弁護士が必要に応じて医療専門家等と連携し、施設の過失を法的に示す。 - 施設・保険会社との交渉代理
施設が賠償を否定する場合や、不十分な金額を提示してくる保険会社に対して、弁護士が法律に基づいた反論を展開。 - 長期的なケア費用の計上
窒息による後遺症が出た場合、在宅ケアや施設利用の追加費用が必要になる可能性があるため、示談で見落とされがちな将来費用をしっかりと算出。 - 再発防止策の提言
示談や和解の中で、食事介助の見直しや職員研修、嚥下機能検査の徹底などを施設に提案し、事故再発を防ぐ。
まとめ
窒息事故は、特に嚥下機能が低下している高齢者や要介護者にとって大きなリスクであり、介護施設は利用者の状態を把握した上で適切な食事形態や介助方法を提供する義務があります。もし施設がこの安全配慮義務を怠ったとみなされる場合、施設運営者は不法行為責任を問われ、損害賠償を負う可能性があります。事故後、家族としては医療機関での治療・診断を最優先に行い、同時に施設の事故報告書を確認し、納得できない部分があれば弁護士に相談して適正な賠償と再発防止策を検討することも選択肢となり得ます。
弁護士法人長瀬総合法律事務所では、介護施設における窒息事故や誤嚥事故に取り組むノウハウを持ち、被害者の権利と安全を守るためのサポートを提供しています。疑問やお悩みを抱えている方は、ぜひご相談ください。
【弁護士法人長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル 】
企業法務に関する問題を解説したYoutubeチャンネルを運営しています。
ぜひご視聴・ご登録ください。
【メールマガジンのご案内】
無料WEBセミナー開催のお知らせや、事務所からのお知らせをメールで配信しています。
ぜひこちらのご登録もご検討ください。