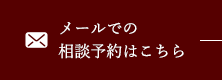2025/09/22 コラム
不当解雇で会社を訴える|解雇が無効になるケースと損害賠償請求の流れ
はじめに
ある日突然、会社から「明日から来なくていい」と解雇を告げられる――。安定した生活の基盤を一方的に奪われることは、労働者にとって死活問題であり、その衝撃と不安は計り知れません。
しかし、日本の法律では労働者は手厚く保護されており、会社が「気に入らないから」といった主観的な理由で労働者を自由に解雇することは固く禁じられています。あなたが受けた解雇は、法的に無効な「不当解告」である可能性があります。
本記事では、解雇が無効になる法的なルールや、不当解雇を争ってご自身の権利を取り戻すための具体的な流れを解説します。
1. 労働者を守る盾:「解雇権濫用法理」とは
労働契約法第16条には、労働者を不当な解雇から守るための極めて重要なルールが定められています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
これは「解雇権濫用法理」と呼ばれ、解雇が有効と認められるには、以下の2つの非常に厳しい条件を両方ともクリアしなければならないことを意味します。
- 客観的に合理的な理由があること
誰が見ても「その理由なら解雇されても仕方がない」と納得できるような、重大な理由が必要です。「上司と合わない」「少し仕事のミスが多い」といった程度では、合理的な理由とは到底認められません。 - 社会通念上相当であること
仮に解雇の理由となりうる事実があったとしても、それに対して「解雇」という労働者に対する最も重い処分を下すことが、社会の常識に照らして妥当か、という点です。会社が注意や指導、配置転換など、解雇を避けるための努力を全くせずにいきなり解雇した場合は、「相当ではない」と判断される可能性が非常に高いです。
この2つの条件を満たさない解雇は、「不当解雇」として法的に無効となります。
2. こんな解雇は「不当」!無効になりやすい典型例
以下に挙げるのは、解雇権濫用法理に基づき、不当解雇として無効と判断されやすい典型的なケースです。
- 能力不足や成績不良を理由とする解雇
十分な教育や指導、改善の機会を与えることなく、一方的に「能力が低い」として行われる解雇。 - 協調性の欠如を理由とする解雇
具体的な業務上の支障を証明できず、単に「性格が合わない」「反抗的だ」といった主観的な理由による解雇。 - 業務外の病気や怪我による休職を理由とする解雇
労働基準法第19条により、業務上の傷病による休職期間中および職場復帰後30日間の解雇は禁止されています。業務外の傷病であっても、即時解雇は無効とされる可能性が高いです。 - 妊娠・出産・育児休業の取得を理由とする解雇
男女雇用機会均等法などで明確に禁止されている差別的な解雇。 - 内部告発を理由とする解雇
公益通報者保護法に守られるべき、会社の不正を然るべき機関に通報したことへの報復として行われる解雇。 - 経営不振による解雇(整理解雇)
いわゆる「リストラ」ですが、これは特に厳格な要件が課されます。次のセクションで詳しく解説します。
整理解雇における「4つの要素」
経営不振を理由とする整理解雇が有効とされるためには、判例上、以下の4つの事項が厳しく審査されます。かつてはこれらが「4要件」として、一つでも欠ければ無効と解釈されていましたが、近年の裁判例では、これらを個別の要件として厳格に判断するのではなく、総合的に考慮すべき「4要素」として捉える傾向にあります。
この司法判断の傾向は、例えば、人員削減の必要性が極めて高い場合には、他の要素が完全に満たされていなくとも解雇が有効と判断される余地がある一方、人員削減の必要性が低い場合には、他の3つの要素が極めて厳格に審査されることを意味します。これは、裁判所が企業の経営判断を尊重しつつも、労働者の保護という観点から事案ごとの実態に即した柔軟な判断を行っていることの表れです。
- 人員削減の必要性
倒産の危機にあるなど、人員削減を行わなければ経営が立ち行かないという客観的な必要性があるか。 - 解雇回避努力
希望退職者の募集、役員報酬のカット、新規採用の停止、配置転換など、解雇を回避するためにあらゆる手段を尽くしたか。 - 人選の合理性
解雇対象者の選定基準が客観的かつ合理的で、その運用が公正であるか。 - 手続きの妥当性
労働組合や労働者に対し、整理解雇の必要性や内容について十分な説明を行い、誠実に協議を尽くしたか。
3. 不当解雇を争う流れと請求できるもの
不当解雇を争う場合、会社に対して以下の請求が可能です。
- 労働者としての地位の確認
解雇が無効であり、今も従業員であることを裁判所に確認してもらう。 - 解雇後の賃金(バックペイ)
解雇されてから問題が解決するまでの期間の給料を、遡って全額請求する。たとえ復職を望まない場合でも、解雇が無効である以上、このバックペイは法的に請求できます。 - 慰謝料
解雇の態様が悪質であった場合などに、精神的苦痛に対する慰謝料を別途請求できる場合があります。
争うための具体的な流れ
- 解雇理由証明書の請求
まずは会社に対し、解雇理由を具体的に記載した書面の交付を求めます。これは後の交渉や裁判で極めて重要な証拠となります。 - 会社との交渉
弁護士を代理人として、解雇の撤回とバックペイの支払いを求めて交渉します。 - 労働審判
交渉で解決しない場合、裁判よりも迅速な解決が期待できる「労働審判」を申し立てます。 - 訴訟(裁判)
労働審判の結果に納得できない場合は、最終手段として「訴訟」を提起します。
4. 解雇を告げられたら、絶対にやってはいけないこと
解雇を告げられた直後の行動が、その後のあなたの運命を大きく左右します。以下の行動は絶対に避けてください。
- 安易に退職届・退職合意書にサインしない
一度サインしてしまうと、「自分の意思で退職に合意した」と見なされ、不当解雇を争うことが極めて困難になります。 - 言われるがまま自己都合退職として処理しない
納得できない場合は、その場で承諾せず、「重要なことですので、持ち帰って検討します」と伝え、すぐに弁護士に相談してください。
まとめ
会社から告げられた解雇理由が、法的に正当なものとは限りません。理不尽な解雇に対して泣き寝入りする必要はなく、あなたの地位と権利を取り戻す道は法的に保障されています。
解雇を言い渡されたら、とにかく何も書類にサインせず、1日でも早く労働問題に詳しい弁護士にご相談ください。それが、あなたの生活と尊厳を守るための最も確実な一歩です。
【弁護士法人長瀬総合法律事務所のYouTubeチャンネル 】
企業法務に関する問題を解説したYoutubeチャンネルを運営しています。
ぜひご視聴・ご登録ください。
【メールマガジンのご案内】
無料WEBセミナー開催のお知らせや、事務所からのお知らせをメールで配信しています。
ぜひこちらのご登録もご検討ください。